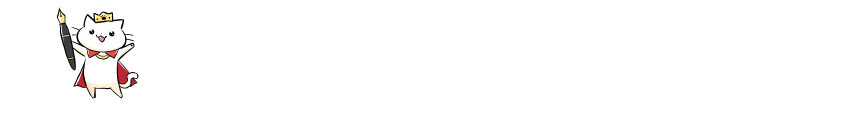小説で笑いを書くのは難しい、とつくづく思う。
それを実感するには、お笑い芸人が作家デビューをしたときに、どんな小説を書いたかを思い返してみるだけでよい。
たとえば大ヒットした又吉直樹の『火花』は、芸人を扱っていて笑いも随所にちりばめられてはいたもののの、基本的には青春を描いた「純文学」だった。
最近のビートたけしの『アナログ』も、ギャグ小説ではなく純愛小説らしい(らしい、というのは読んでないからなのだけど)
他にも、劇団ひとりの『陰日向に咲く』や、太田光の『幻の鳥』や、水嶋ヒロの『KAGEROU』、など、どれもがストレートなギャグ小説ではなかったことは火を見るよりも明らかだ。(まあ、水嶋ヒロはそもそも芸人じゃないから仕方ないのだけど)
もちろん、彼らは日頃テレビで散々笑いをやっているわけだから、小説ではいつもと違ったジャンルを書いてみたくて、ギャグ小説ではなく、純文学や恋愛やSFを書いた、という見方もできるだろう。
だが、僕はこう考えている。
彼らは、笑える小説を書かなかったのではなく、書けなかったのだ。
小説の笑いのよくあるパターンとして「キャラクター」としての笑いがある。
少し前にヒットした『謎解きはディナーのあとで』みたいに、メインキャラクタ-(大抵は男女ペア)たちの掛け合いで笑わすという手法。
最近、一般文芸でもラノベでも、このパターンの笑いが多く、似たような作品がたくさん出ている。
こういうキャラの笑いにも面白いものはあるのだけど、何か物足りなさを感じていた。
物語としての笑い。構造としての笑い。実験としての笑い。そして、小説だからできる笑い。
その微かな可能性を、僕はずっと探し求めていた。
そんなとき、元芸人の藤崎翔が書いた『神様の裏の顔』に出会った。
読みやすいモノローグの文体の連続。次々に飛んでくるギャグ。くり返されるどんでん返しにより、ユーモアとミステリーがリンクしていく。
「ああ、私が読みたかったのはこういう小説なんだよ!!」
と思わず快哉を叫びたくなった。
小説で笑いを書くのは確かに難しい。
だが、できないことではない、ということを、藤崎翔は証明してくれたんだ。
●おすすめ関連記事
→kindle unlimited(キンドルアンリミテッド)は読書家におススメ【 Prime Readingとの違い】はコチラ
→小説を書くときに役に立つ道具まとめ【執筆環境・パソコンソフト・ノート】はコチラ
→『ぼぎわんが、来る』澤村伊智~日常と非日常の恐怖の融合~はコチラ