読み終わってすぐに、ボロボロ泣けて素晴らしい本だったけど、ちゃんと売れるのかな、と心配になった。
なにより、扱っているテーマが地味である(その代わり、本の装丁はオレンジ色で派手だが…)。
『55歳からのハローライフ』は、5人の中高年の主人公のそれぞれの物語の短編(中篇?)集だ。
彼らはみな、経済面やパートナーとの不和などの問題を抱えていて、なんとか人生を変えたい、と思っている。
大きな事件も起こらなければ、驚くような大どんでん返しもない。
どこにでもありそうな日常の、誰にでも訪れそうな困難が、丁寧に描かれている。
55歳ぐらいの人は興味があって買うのかもしれないが、それ以外の年代の人で、しかも村上龍の新作なら必ず買うというほどのファンではない人で、買う人が少ないのではないか、と心配になったのだ。
『愛と幻想のファシズム』や『半島を出よ』などで見せた、圧倒的な情報から壮大な物語を構築していくスタイルは出てこなければ、『限りなく透明に近いブルー』や『コインロッカー・ベイビーズ』のような過激なテーマや題材も出てこなければ、『エクスタシー』や『トパーズ』のような特徴的な文体も出てこなければ、『69』や『昭和歌謡大全集』のような底抜けの明るさとユーモアも、今回の本にはほとんど出てこない。
それでもこの本には、村上龍の真骨頂が表れている、と思う。
結婚相談所で登録する写真を撮るときに、「ブラウスの上のボタンをできれば二つ外したほうがいい」と相談員に言われて、女性の主人公が泣いてしまいそうになるシーンがある。
日本は、中高年になってから結婚相手を探すときに、ブラウスの上のボタンを二つ外して写真を撮らなければ難しいような、そんな世の中だ、というミもフタもない現実を村上龍は徹底的に描いて読者に突きつける。
また、腰痛を抱えていたり体調を壊していたりして体が思うように動かない登場人物たちにとって、東京駅から出る高速バスに時間までに辿り着けるかどうかが、ドラマになる。
だが、まるで巨大な軍艦のような東京駅が見えてきたとき、福田が突然苦しがり、咳き込んで、嘔吐をはじめた。
この物語を読んでいると、どんどん気分が暗くなっていく。中高年になって楽しいことなんてほとんどないじゃないか、という気さえしてくる。
シリアスな状況は中高年の問題だけではない。全ての世代の人が、みなそれぞれに、何らかの不幸を背負って生きている。
飲み物がこの本の希望の象徴であったように、希望は、確かにある。
登場人物たちは皆、必死に希望に手を伸ばし、歩き出す。
それはとても小さな、それでも確実な一歩だ。
厳しい現実から逃げずに向き合い、その中で必死に希望を探し出し、それを表現する。
村上龍はそんなことができる数少ない作家の一人であり、そのような誠実でフェアな生き方こそが、氏の作品を好きになった最大の理由なのだと思う。
→村上龍『69 sixty nine(シクスティナイン)』の名言「唯一の復しゅうの方法は…」はコチラ
→kindle unlimited(キンドルアンリミテッド)は読書家におススメ【 Prime Readingとの違い】はコチラ
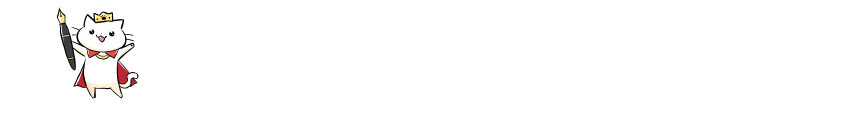











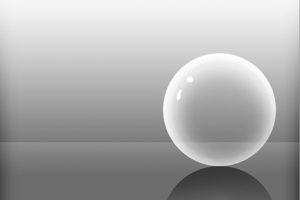

コメントを残す